こんにちは、【街の小さなピアニスト音楽教室】都筑教室の森山です。
ピアノレッスンの中で声を出して歌うことはたくさんあります。
ピアノが弾きたいのに、歌うの?と思われる方もいらっしゃるでしょうか。
・繰り返し歌うことで音を覚えて間違えにくくなる
・初見の楽譜を歌ってみることで、譜読みの練習になる。
などなどこれらの効果もありますが、とても重要なことは、メロディーの(音楽の)エネルギーを感じるためです。
この感覚があるかないかでピアノの演奏が大きく変わります。
ですので導入の段階から歌うことはたくさんしています。
歌はクラッシック音楽の原点
音楽の父として有名なバッハのいた時代よりももっと昔、教会で歌われていた聖歌がクラシック音楽のルーツと言われています。
最初は歌だけ、次第にハモったり伴奏がついてハーモニーが生まれていったそうです。
音楽そのものの起源ははっきりしていないようですが、もっとさかのぼれば、
狩りが成功した時の感情を乗せた声で喜びの合唱が起こったり、豊作の祈りや収穫の感謝を声に表しながら踊ったりしていたのでしょうね。
少し逸れましたが、ピアノも、声ではありませんが歌うんです。
歌われていない音たちは、ある意味〈音楽〉とは言えないのかもしれません。
ありがちなロボット現象
ピアノでよくあるのが、無機質で無表情な音楽・演奏になることです。
声を出して歌うことを考えてみると‥
高い声を出すときには、グッとお腹や喉の筋肉に力が入ったり、音程が変わるだけでも体に少なからず変化はありますよね。
音程がどんなに変わろうが身体に何の変化もありません!という人はいないはず。
また、歌うにはブレス(息継ぎ)も必要ですね。
ブレスをせずに歌い続けられる人もいません。
それが出来るのは‥ロボット、A.I.ですね。
ピアノは良くも悪くも鍵盤を押せば難なく音自体は出せてしまいますので、ただ楽譜に書かれている音だけを追えば、一通り演奏することはできます。
でもそれが、何の揺らぎもない生命感の無いロボットの音楽になってしまう要因でもあります。
人が演奏しているのに聴こえてくるのはロボットの音楽という、不自然なものになってしまうんです。
音の羅列であり、音の間違いは無いでしょう?という答え合わせ、でしかないようにも聴こえます。
作曲家が描いていたのはそんな音楽ではないはずです。
ピアノも、歌っているような揺らぎのある演奏でなければ、その曲の温かみ・切なさ・苦しみ・楽しさ‥伝わるはずのものが伝わってきません。
〈音楽は歌うこと〉です。
歌えば自然と
声楽家は身体が楽器といいます。
自分が楽器となり、音楽を奏でてみる(歌ってみる)ことで分かることがあります。
歌ってみると、この部分(音程)は苦しいな、力んじゃうな、とか、このフレーズはスーっと歌いやすいな、とか、ここは小さい声がいいな、など歌の中にエネルギーの変化を感じられます。
そして自らの身体で創り出したように、ピアノの音でも歌うように音楽を創ります。
また、声を出して歌ってみると、子どもたちもブレスは自然と吸うべき時にしています。
ピアノでもそのように音のブレスを入れると、生きた演奏に近づきます。
少し前のブログで歌うことについての記事があります。
レッスンではこのようなステップを踏んで歌を取り入れていて、歌いなさい!と強制したり、イヤイヤ歌っているような状況になることはありませんので、ご安心くださいね。
普段のピアノの練習でも、ロボットになっていないかな?とぜひ歌ってみてください。


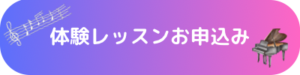
-300x203.png)

-300x203.png)

-300x203.png)
-300x203.png)
コメント